講師から
先週、全ての生徒さんにお渡しした「音符カード早読み大会」のお便りですが、生徒の皆さんは少しでも音読み学習をしているでしょうか?ちょうど休日が続きますし、隙間時間を見つけてパッと読めるようにしていきましょう。
早速、今日のピアノレッスン中に皆さんにやってもらいました。今日は園児さんから中学生のレッスンをしましたが、レベル1に悪戦苦闘する姿も。緊張もあるのかなぁ?ヘ音記号の音が出てくると数えています。数えて読んでしまうと制限時間内には読めないので、合格は難しくなります。
今日1番の快挙は、レベル3まで合格した中学生。時間がなくて、レベル4の挑戦はできなかったのですが、ひょっとしたらレベル4でも合格したかもしれませんね。この生徒さんはピアノを習い始めたのがとても遅く、4年生の秋でした。かなり遅いスタートでしたが、私の怖いレッスン(?)に耐えて頑張っています。努力家です。
音読みは年齢が小さい、大きいは関係ありません。同じ曲を長い期間かけて練習していては、小さい時にピアノを始めても、音を読むことはできません。次から次に、短くても新しい曲を練習していくこと、できれば音符カードで音読みを取り入れることが、読めるようになる条件になります。さあ、気を引き締めて頑張っていきましょう。
しつこいですが何回も言います。音符の長さがきちんと理解できていない、正しく弾けていない間は、数えながら練習しなきゃダメです。
生徒さんの中には、付点四分音符が1つと半分の長さであることがわかっているのに、いざ弾いてみると、1つと半分の長さになっていない・・・どうして?やっぱり数えて練習していないのです。音符の長さがあやふやで、短くなったり長くなったりしています。頭でわかっていても、正しく弾き分けることができなければ、理解していることにならないと思うのです。
これまでに何人もの生徒さんのレッスンを通してはっきり言えることは、「数えなくなったら、ピアノが下手になっていく」ということ。レッスンが進むにつれて音符の種類は増えていきます。一つ一つの音符が本当にわかっていなければ、弾き分けることは難しくなります。適当な音符の長さで弾いていたのでは、何拍子の曲なのかもわからなくなります。
これから先、自分が弾きたい曲の練習をする場合でも、音符の長さは正しく弾かなければ、何の曲なのかもわからなくなります。せっかく習ったピアノなのに、弾きたい曲も楽しめないなんて残念です。お子様が数えながら練習しているかどうか、保護者の方にも少し気にしていただければと思います。
生徒さんの中には、付点四分音符が1つと半分の長さであることがわかっているのに、いざ弾いてみると、1つと半分の長さになっていない・・・どうして?やっぱり数えて練習していないのです。音符の長さがあやふやで、短くなったり長くなったりしています。頭でわかっていても、正しく弾き分けることができなければ、理解していることにならないと思うのです。
これまでに何人もの生徒さんのレッスンを通してはっきり言えることは、「数えなくなったら、ピアノが下手になっていく」ということ。レッスンが進むにつれて音符の種類は増えていきます。一つ一つの音符が本当にわかっていなければ、弾き分けることは難しくなります。適当な音符の長さで弾いていたのでは、何拍子の曲なのかもわからなくなります。
これから先、自分が弾きたい曲の練習をする場合でも、音符の長さは正しく弾かなければ、何の曲なのかもわからなくなります。せっかく習ったピアノなのに、弾きたい曲も楽しめないなんて残念です。お子様が数えながら練習しているかどうか、保護者の方にも少し気にしていただければと思います。
ピアノの上達と音読みがパッとできるかどうかは、やっぱり比例しています。レベル4を合格された生徒さんの紹介です。一気にレベル4まで合格された生徒さんは、中学生。音楽が好きで、ピアノが好きで、吹奏楽部でも活躍されています。
音符カード読みも、大抵は1~2回失敗(タイムオーバー)して合格する生徒さんが多いのですが、この生徒さんは全て1回合格。さっさと終わってしまいました!いやいや、私としてはつまんな〜い・・・なんてことはありませんが、「やっぱりね」と言う当然の結果です。レッスンで、音ミスを指摘することがほとんどありません。音のミスがないので、存分に表現力をつけるレッスンができるのです。
音ミスが多い生徒さんの場合は、極端なことを言えば、レッスン時間中ずっと音ミスの注意ばかりすることになります。「こう弾いて欲しい」「ここはもっと盛り上げて〜」と言うレッスンからは程遠いです。きっと生徒さんも、音ミスばかり指摘されて楽しくないと思います。
ピアノのレッスンって音ミスを指摘されるレッスンではないと思います。その為にも、せめて五線の中にある音符くらいは、サッと読めるようにしたいもの。この生徒さんのように、好きな曲を素敵に弾けるようになっていきましょうよ!
音符カード読みも、大抵は1~2回失敗(タイムオーバー)して合格する生徒さんが多いのですが、この生徒さんは全て1回合格。さっさと終わってしまいました!いやいや、私としてはつまんな〜い・・・なんてことはありませんが、「やっぱりね」と言う当然の結果です。レッスンで、音ミスを指摘することがほとんどありません。音のミスがないので、存分に表現力をつけるレッスンができるのです。
音ミスが多い生徒さんの場合は、極端なことを言えば、レッスン時間中ずっと音ミスの注意ばかりすることになります。「こう弾いて欲しい」「ここはもっと盛り上げて〜」と言うレッスンからは程遠いです。きっと生徒さんも、音ミスばかり指摘されて楽しくないと思います。
ピアノのレッスンって音ミスを指摘されるレッスンではないと思います。その為にも、せめて五線の中にある音符くらいは、サッと読めるようにしたいもの。この生徒さんのように、好きな曲を素敵に弾けるようになっていきましょうよ!
色は今までと同じですが、材質が少し良くなりました。クッションも新しくしてもらったので、少し分厚くなった気がします。いい感じの仕上がりです。
椅子は戻ってきましたが、レッスンで使用する椅子は、戻ってきた椅子でもワイドな横長椅子でも、どちらでも構いません。生徒さん自身が気に入った方の椅子を選んでください。7日(日)まではレッスンもお休みです。みんな、楽しいことの真っ最中かな?月曜日からのレッスンを、新しい椅子と一緒に待っていますね。
5月のステップ参加に向けて、練習を頑張っている生徒さん。初めてのステップ参加です。1週間ごとのレッスンで、メキメキ上達していることがわかります。
どの生徒さんよりも1番たくさん練習していると思います。本当にそう思ってます。でも、私はまだ褒めません。逆に「ステップまでは気を抜かないで。ステップまで頑張ろう。ステップが終わったら、ちょっとゆっくりしようね。」と言っています。ずっと頑張り続けることは誰だって嫌になっちゃいます。マラソンだって、ゴールまでだから頑張れるのと一緒。ピアノもゴールが分かっていると、頑張れませんか?
以前に、ステップ参加の生徒さんに「曲が仕上がってきたね〜。上手だよ。この調子でね。」と声かけをしたことがあるのですが、その途端、あんまり練習をしなくなってしまって、本番前に曲が崩れてしまったことがありました。仕上がった状態のままキープして欲しかったのですが、保護者の方曰く「上手になったと褒められたことで、逆に練習をしなくなった」とのこと。う〜ん、モチベーションを維持するのって難しい。
初参加の生徒さんとの連休前のレッスンで、「ステップまで頑張れる?」「大丈夫。毎日練習してる。」と、心強い返事をもらいました。きっと頑張ってくれると思います。わかっているからね。1番練習を頑張っているってこと。あともう少し、走り続けよう。
どの生徒さんよりも1番たくさん練習していると思います。本当にそう思ってます。でも、私はまだ褒めません。逆に「ステップまでは気を抜かないで。ステップまで頑張ろう。ステップが終わったら、ちょっとゆっくりしようね。」と言っています。ずっと頑張り続けることは誰だって嫌になっちゃいます。マラソンだって、ゴールまでだから頑張れるのと一緒。ピアノもゴールが分かっていると、頑張れませんか?
以前に、ステップ参加の生徒さんに「曲が仕上がってきたね〜。上手だよ。この調子でね。」と声かけをしたことがあるのですが、その途端、あんまり練習をしなくなってしまって、本番前に曲が崩れてしまったことがありました。仕上がった状態のままキープして欲しかったのですが、保護者の方曰く「上手になったと褒められたことで、逆に練習をしなくなった」とのこと。う〜ん、モチベーションを維持するのって難しい。
初参加の生徒さんとの連休前のレッスンで、「ステップまで頑張れる?」「大丈夫。毎日練習してる。」と、心強い返事をもらいました。きっと頑張ってくれると思います。わかっているからね。1番練習を頑張っているってこと。あともう少し、走り続けよう。
皆さんに読んでいただいているこの「講師から」欄ですが、時々、写真を入れることにしました。実は、5月の記事も2箇所だけ写真が入っているのですが・・・。
まだまだ進化途中のホームページです。写真も前々から入れてみたいと思っていたものの、なかなか覚えることがたくさんあり過ぎて、トホホ状態です。高校生だった息子が作ってくれたホームページなので、業者さんのように綺麗なホームページではありませんが、それでもここまでの形になりました。写真ひとつ入れるのにも、まだまだ子供に怒られながら(?)やっています。
さて、GWも終わり今日から通常レッスン再開しました。音符カード読みも始まりますよ〜。音符カード合格の秘訣は、お家で音読み学習をすることに尽きます。お家で学習をしてきた生徒さんは、順調に一つ一つ合格をしています。皆さん、ヘ音記号で時間を取られているようですから、ヘ音記号を重点的に学習すると良いでしょう。憧れの曲を素敵に弾けるようになるための第一歩ですから、音読みは頑張ってマスターしましょうね。
まだまだ進化途中のホームページです。写真も前々から入れてみたいと思っていたものの、なかなか覚えることがたくさんあり過ぎて、トホホ状態です。高校生だった息子が作ってくれたホームページなので、業者さんのように綺麗なホームページではありませんが、それでもここまでの形になりました。写真ひとつ入れるのにも、まだまだ子供に怒られながら(?)やっています。
さて、GWも終わり今日から通常レッスン再開しました。音符カード読みも始まりますよ〜。音符カード合格の秘訣は、お家で音読み学習をすることに尽きます。お家で学習をしてきた生徒さんは、順調に一つ一つ合格をしています。皆さん、ヘ音記号で時間を取られているようですから、ヘ音記号を重点的に学習すると良いでしょう。憧れの曲を素敵に弾けるようになるための第一歩ですから、音読みは頑張ってマスターしましょうね。
練習時にお世話になっているメトロノームですが、一定の速さで弾けるようにする為には、効果を発揮する道具です。でも、本番の舞台では使いませんよね。
メトロノーム練習をやめた途端、今までとは全く違う速さで弾いてしまう場合は、まだ自分の体がその曲の速さを覚えていないからです。ステップなど速さが違う曲を続けて弾く場合、それぞれの曲の速さを覚えておかなければいけません。体に曲の速さを覚えさせるには、正しい曲の速さで何度も何度も練習することが重要になってきます。
まずはメトロノームをかけて、正しい速さで弾く練習、次にメトロノームをかけないで同じ速さで弾く練習、これを交互に繰り返します。毎日この練習を繰り返していると、自然と体が曲の速さを覚えてしまいます。練習段階ではゆっくりの速さでおさらいをしていたとしても、本番近くなってきたら、本番通りの速さで練習するようにしましょう。
本番当日に慌てない為には、曲を弾く前に、頭の中で2~3小節メロディーを確認する(頭の中で歌う)と良いでしょう。そうすることで、落ち着いて弾き始めることができます。何事も慌てるのは損!どっしりと構えて自信を持って演奏しましょう。
メトロノーム練習をやめた途端、今までとは全く違う速さで弾いてしまう場合は、まだ自分の体がその曲の速さを覚えていないからです。ステップなど速さが違う曲を続けて弾く場合、それぞれの曲の速さを覚えておかなければいけません。体に曲の速さを覚えさせるには、正しい曲の速さで何度も何度も練習することが重要になってきます。
まずはメトロノームをかけて、正しい速さで弾く練習、次にメトロノームをかけないで同じ速さで弾く練習、これを交互に繰り返します。毎日この練習を繰り返していると、自然と体が曲の速さを覚えてしまいます。練習段階ではゆっくりの速さでおさらいをしていたとしても、本番近くなってきたら、本番通りの速さで練習するようにしましょう。
本番当日に慌てない為には、曲を弾く前に、頭の中で2~3小節メロディーを確認する(頭の中で歌う)と良いでしょう。そうすることで、落ち着いて弾き始めることができます。何事も慌てるのは損!どっしりと構えて自信を持って演奏しましょう。
今日のレッスンでテンションが下がってしまった未就学児の生徒さん。綺麗に音をつなげて弾く練習がうまくいかなくて、やる気ダウンしてしまったのです。
音を繋げる、つまりレガートで弾くことは、ピアノを習い始めて1番に襲ってくる壁です。こればっかりは、どんなに時間がかかってもマスターしてもらうしかありません。私も良いお手本と悪いお手本を弾き比べたりするのですが、小さなお子様だと理解してもらうのに時間がかかります。
1つの練習方法として、ピアノではなく、テーブルの上などで指を動かしてみましょう。テーブルの上で滑らかに12345、54321、1515、1414など、ゆっくりで構わないので、指を交互に動かしてみましょう。ピアノの鍵盤ではできなくても、テーブルの上だとできる場合があります。テーブルでできるようになったらピアノの鍵盤で挑戦するのですが、まずは片手づつゆっくり練習から。急ぐ必要はないので、丁寧な練習を心がけましょう。
ピアノに限らず、努力した結果できるようになったと言う「成功体験」は必要です。「成功体験」を積み重ねることで自信がついたり、次の意欲がでてきて前向きに進んでいくことができるようになります。できなくて諦めることは簡単。でもそれでは諦めグセがついてしまいませんか?何とか乗り越えて欲しいなぁと思った出来事でした。頑張って。
音を繋げる、つまりレガートで弾くことは、ピアノを習い始めて1番に襲ってくる壁です。こればっかりは、どんなに時間がかかってもマスターしてもらうしかありません。私も良いお手本と悪いお手本を弾き比べたりするのですが、小さなお子様だと理解してもらうのに時間がかかります。
1つの練習方法として、ピアノではなく、テーブルの上などで指を動かしてみましょう。テーブルの上で滑らかに12345、54321、1515、1414など、ゆっくりで構わないので、指を交互に動かしてみましょう。ピアノの鍵盤ではできなくても、テーブルの上だとできる場合があります。テーブルでできるようになったらピアノの鍵盤で挑戦するのですが、まずは片手づつゆっくり練習から。急ぐ必要はないので、丁寧な練習を心がけましょう。
ピアノに限らず、努力した結果できるようになったと言う「成功体験」は必要です。「成功体験」を積み重ねることで自信がついたり、次の意欲がでてきて前向きに進んでいくことができるようになります。できなくて諦めることは簡単。でもそれでは諦めグセがついてしまいませんか?何とか乗り越えて欲しいなぁと思った出来事でした。頑張って。
近い間に、連弾のレッスンを始める約束をした生徒さんがいらっしゃいます。生徒さんの弾きたい曲や好みの曲を聞いているので、今は、どのテキストにしようかと研究中です。連弾のテキストもたくさん出版されていて、レベルもありますが、曲の種類もありとあらゆる曲が連弾用にアレンジされています。
私は昔から、連弾や2台のピアノで合わせる曲、他の楽器の伴奏などの合わせものが好きで、よく他の方と一緒に演奏しました。一人ではないので責任も重大ですが、楽しさは2倍です。最初から難しい曲に挑戦すると楽しくないので、簡単な曲から始めて、少しづつ大曲に挑戦できたらいいなぁと考えています。クリスマス会では、カッコよく連弾したいなぁなんて・・・。生徒さん、一緒にやってくれるかな?
ある程度の音が読めて、両手で弾けるようになっている生徒さんなら連弾も可能です。普段のテキストの曲と交互にやったり、余裕のある生徒さんならテキストと同時に進めたり、いろいろな方法ができますので、連弾をやってみたいと思われる生徒さんがいらっしゃいましたら、声をかけてくださいね。あっ、でも練習がきちんとできる生徒さん限定です。楽しみに待っています。
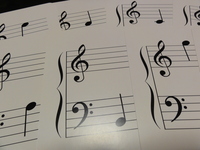 一通り、音符カード読みが終了しました。最初から「やらない」と言う生徒さんも何名か見られましたが、結構、楽しく取り組んでもらったようです。
一通り、音符カード読みが終了しました。最初から「やらない」と言う生徒さんも何名か見られましたが、結構、楽しく取り組んでもらったようです。以前に、中学生の生徒さんのレベル4の合格の話をさせてもらいましたが、レベル4を合格された小学6年生の生徒さんもいらっしゃいます。皆さん、負けていられませんよ〜。この生徒さんは努力家で、習い始めの頃は自分で楽譜に1と2と3と・・・などの数え方をびっしり書いてくださっていました。思うように出来ない時は悔しくて、泣いてしまうこともありました。その生徒さんも6年生になられて、早いものです。小さい頃が懐かしく感じます。
レベル4の合格は逃してしまったものの、レベル3までを合格している生徒さんもいらっしゃいます。やはり、レベル3までを合格している生徒さんは、普段のレッスンが順調に進んでいる場合がほとんどです。音符カード読みは、あともう一息のところまできていますから、頑張って終わらせましょう。
小学生でも中学生でも、また、未就学の生徒さんでも、音符カード読みは訓練次第で読めるようになるものです。音ミスばかりを注意されないよう、音読み練習をしっかりしましょう。
テキストが終了した生徒さんが続いたこともありますが、音符カードの音読み大会をしていることもあって、BOXオープンが続いています。高校生の生徒さんは、いきなりのレベル4を1回目で合格されました。どんな曲でも弾きこなす生徒さんなので、当然の結果です。
未就学児の生徒さんや小学生の生徒さん向けに設置した「がんばったBOX」なので、入っている文具も小さな生徒さん向けのものが多いのですが、中学生、高校生の生徒さんにも使っていただけるように付箋なども用意してあります。音符カード読みを合格された高校生の生徒さんは、試験勉強に便利な付箋を持って帰られました。
立て続けにBOXオープンがあったので、中のものも少なくなってきました。次にBOXをオープンしてくれるのはどの生徒さんでしょうか?
楽譜の中には、強く弾いたり弱く弾いたりする強弱記号が出てきていると思います。皆さんは、この強弱記号を気にして弾いていますか?
自分では強く、弱くをつけて演奏しているつもりでも、聴いている人がそれを感じていなかったら、強弱の表現がついているとは言えません。ピアノの演奏は、「聴いている人がどう感じているのか」を考えて演奏しましょう。強い音があるから弱い音が目立ちますし、弱い音があるから強い音が目立ちます。逆のものがあるから、感じることができると思いませんか?
「やっているつもり」の「つもり演奏」をしている生徒さんは、いつもよりも少し大げさに表現してみると良いでしょう。他の人に感じてもらう演奏をするには、案外、大げさがちょうど良いかもしれません。様々な生徒さんの演奏を聴いていると、おとなしい生徒さんは、表現も控えめな感じがします。もっと、音楽を爆発させてもいいのにな〜と、思います。
ただし、強い音が欲しいからと言って、乱暴な音では困ります。強い音と乱暴な音は、似ているようで違います。これもまた、聴いている人が乱暴だと感じていたら、乱暴な音になります。難しいですね。自分の音が乱暴な音なのか強い音なのか、聴きわけることができれば、弾きわけることもできます。音の響きをよく聴いて、綺麗な音を目指しましょう。
自分では強く、弱くをつけて演奏しているつもりでも、聴いている人がそれを感じていなかったら、強弱の表現がついているとは言えません。ピアノの演奏は、「聴いている人がどう感じているのか」を考えて演奏しましょう。強い音があるから弱い音が目立ちますし、弱い音があるから強い音が目立ちます。逆のものがあるから、感じることができると思いませんか?
「やっているつもり」の「つもり演奏」をしている生徒さんは、いつもよりも少し大げさに表現してみると良いでしょう。他の人に感じてもらう演奏をするには、案外、大げさがちょうど良いかもしれません。様々な生徒さんの演奏を聴いていると、おとなしい生徒さんは、表現も控えめな感じがします。もっと、音楽を爆発させてもいいのにな〜と、思います。
ただし、強い音が欲しいからと言って、乱暴な音では困ります。強い音と乱暴な音は、似ているようで違います。これもまた、聴いている人が乱暴だと感じていたら、乱暴な音になります。難しいですね。自分の音が乱暴な音なのか強い音なのか、聴きわけることができれば、弾きわけることもできます。音の響きをよく聴いて、綺麗な音を目指しましょう。
神田ピアノ教室では、自分の力で楽譜を読めるように指導しています。そのために、音符カード早読み大会もやっています。そこで一つ、保護者の方に注意していただきたいことがあります。
お子様の練習曲を、お子様よりも先に演奏するのはいけません。子供って大人が考えているよりも耳が良いので、音やリズムなど、一度聴いたものを再現してしまいます。音当てのようにして真似して弾いてしまうのです。これを繰り返していると、楽譜を読むことが苦手になり、結局は楽譜が読めなくなってしまいます。
私のピアノのレッスンでも、楽譜が読める生徒さんならば、「こんな感じだよ」と弾いて聴いてもらうこともありますが、導入期の大切な段階では、最初にお手本を聴いてもらうレッスンはしていません。自分の力で音を読みリズム(音符の長さ)を理解してもらいたいからです。
大手の音楽教室のグループレッスンの生徒さんにありがちなのが、「弾けるけれど楽譜が読めない」ということ。グループレッスンでは、一人一人に指導が行き渡らないために、先生の演奏を元に感覚で弾いてしまうのです。ただ、グループレッスンがダメだということではなく、読譜力の面では力はつきませんが、みんなと合わせるアンサンブルの楽しさはグループでしか味わえません。
耳で聴いて再現する「耳コピ」の能力は、これはこれで素晴らしいと思いますが、まずは読譜力をつけることを重視していますので、お子様の前では演奏を自粛してほしいと思います。
お子様の練習曲を、お子様よりも先に演奏するのはいけません。子供って大人が考えているよりも耳が良いので、音やリズムなど、一度聴いたものを再現してしまいます。音当てのようにして真似して弾いてしまうのです。これを繰り返していると、楽譜を読むことが苦手になり、結局は楽譜が読めなくなってしまいます。
私のピアノのレッスンでも、楽譜が読める生徒さんならば、「こんな感じだよ」と弾いて聴いてもらうこともありますが、導入期の大切な段階では、最初にお手本を聴いてもらうレッスンはしていません。自分の力で音を読みリズム(音符の長さ)を理解してもらいたいからです。
大手の音楽教室のグループレッスンの生徒さんにありがちなのが、「弾けるけれど楽譜が読めない」ということ。グループレッスンでは、一人一人に指導が行き渡らないために、先生の演奏を元に感覚で弾いてしまうのです。ただ、グループレッスンがダメだということではなく、読譜力の面では力はつきませんが、みんなと合わせるアンサンブルの楽しさはグループでしか味わえません。
耳で聴いて再現する「耳コピ」の能力は、これはこれで素晴らしいと思いますが、まずは読譜力をつけることを重視していますので、お子様の前では演奏を自粛してほしいと思います。
ピアノを演奏するときの姿勢って気にしていますか?とても上手に仕上がっているのに、自信がなく見えてしまうのは、姿勢に問題があるかもしれません。
ピアノを弾くときに、あまり下ばかり(鍵盤ばかり)見て弾いていると、音も頼りな〜く聴こえてしまいます。見た目って大事です。暗譜で弾くからといって鍵盤ばかり見ているわけではありません。視線を少し鍵盤から離して音楽に酔いしれたり、音の響きに耳を傾けたりしながら演奏します。
例えば舞台に向かって歩くときでも同じで、猫背で下を向いて歩いていると、上手に演奏しそうには見えません。逆に堂々と前を向いて歩いていると、それだけで上手な演奏者に見えませんか?
ピアノを演奏するときには、偉そうなくらいがちょうどいいです。胸を張って綺麗な手の形で落ち着いて演奏しましょう。堂々とした姿勢から、堂々とした音は生まれます。自信を持ってレッスンに臨んでください。
ピアノを弾くときに、あまり下ばかり(鍵盤ばかり)見て弾いていると、音も頼りな〜く聴こえてしまいます。見た目って大事です。暗譜で弾くからといって鍵盤ばかり見ているわけではありません。視線を少し鍵盤から離して音楽に酔いしれたり、音の響きに耳を傾けたりしながら演奏します。
例えば舞台に向かって歩くときでも同じで、猫背で下を向いて歩いていると、上手に演奏しそうには見えません。逆に堂々と前を向いて歩いていると、それだけで上手な演奏者に見えませんか?
ピアノを演奏するときには、偉そうなくらいがちょうどいいです。胸を張って綺麗な手の形で落ち着いて演奏しましょう。堂々とした姿勢から、堂々とした音は生まれます。自信を持ってレッスンに臨んでください。
レッスンで「では、弾いてみて」との言葉かけ後に弾いてくれるのですが、最初の一音目から間違った音や、ぐしゃっとした何とも響きの悪い音で弾き出してしまう生徒さん。これって信じられない行動なのですが、どうでしょうか?
曲の途中での間違った音ならわかります。ミスタッチをすることだってあるでしょう。でもでも、一音目の間違いって明らかに用意不足。今から音楽が始まるっていう時なのに、鍵盤の確認もしないまま弾き出しているということ。それはやっぱりおかしいでしょう。鍵盤の確認はもちろんですが、心の準備も必要です。これから自分の音楽が始まる大事な一音目です。落ち着いて弾き出す余裕が欲しいもの。
私がピアノを習っていた小さい頃、ピアノの先生に「弾く前には2〜3小節分、頭の中で弾く曲を奏でてから弾き始めなさい」と言われていました。本当にそうだと思います。どんな曲だったかな、どんな速さで弾くんだったかな、と思い返すことが大切なのです。それは、レッスンでも家での練習でも同じこと。手の準備、心の準備を整えてから弾き始めるようにしましょう。
曲の途中での間違った音ならわかります。ミスタッチをすることだってあるでしょう。でもでも、一音目の間違いって明らかに用意不足。今から音楽が始まるっていう時なのに、鍵盤の確認もしないまま弾き出しているということ。それはやっぱりおかしいでしょう。鍵盤の確認はもちろんですが、心の準備も必要です。これから自分の音楽が始まる大事な一音目です。落ち着いて弾き出す余裕が欲しいもの。
私がピアノを習っていた小さい頃、ピアノの先生に「弾く前には2〜3小節分、頭の中で弾く曲を奏でてから弾き始めなさい」と言われていました。本当にそうだと思います。どんな曲だったかな、どんな速さで弾くんだったかな、と思い返すことが大切なのです。それは、レッスンでも家での練習でも同じこと。手の準備、心の準備を整えてから弾き始めるようにしましょう。
午前中から何人かの生徒さんが出演されましたが、今回、初めてのステップ参加で初めての大きな舞台に立たれた生徒さんも。でも、堂々と落ち着いて演奏することができました。きっと緊張もされたと思います。何度か舞台に立つことを経験していく間に、舞台度胸もつきますし、緊張も心地よい緊張に変わっていくことでしょう。
ステップでは、アドバイザーの先生3名からアドバイスをいただけます。良かったところや気をつけるといいところなど、他の先生からアドバイスをいただけることは励みにもなります。良いところは素直に喜んで、気をつけるべきところは注意して、これからの練習につなげていけると良いですね。
なかなか自分の演奏を客観的に聴くことはできないのですが、ビデオを録画されている場合は、一度自分の演奏を聴いてみると良いと思います。音のバランスや盛り上げ方など、できているようで思うように表現できていないことがわかる場合もあります。自分の演奏を良い方向に持っていく場合に、録音したものを聴くことはとても有効な手段です。日頃の練習曲でも時々、録音してみると良いでしょう。
ステップに参加すると、同年代のお友達の演奏を聴くこともできますし、演奏マナーや聴衆マナーも学ぶことができます。ステップに参加を考えている生徒さんは、ご相談ください。
神田ピアノ教室では正しいリズムで演奏するために、自分で数えながら(声に出しながら)練習するように指導しています。「1,2,3,1,2,3・・・」は3拍子ですが「1,2,さ〜ん」は何拍子になると思いますか?
数字的には3までしか数えていないので、小さなお子様の場合は3拍子であると思っていることが多いのですが、3拍目の3がさ〜んって間延びしていると、実際には4拍子になっています。3拍子って難しいですよね。
人間は「1,2,1,2」で歩くので、2拍子や4拍子は体に馴染んでいるのですが、3拍子になると、どうしても3拍目が長くなってしまう生徒さんがいらっしゃいます。3拍目を数えたらすぐに次の1拍目がやってくることを、根気よく覚えていくしかありません。生徒さんが慣れるまでは、保護者の方が横について「1,2,3,1,2,3」と一緒にカウントするのがよいでしょう。ただし、生徒さんも一緒に声に出して数えることが大切です。
いつまでも生徒さんの横で数えてあげていると、生徒さん自身が数えることをやめてしまいますからオススメできません。「自分で数えながら弾く」ことが重要なのであって、正しくリズムを理解できているかの目安になりますので、数えながら練習を徹底しましょう。
数字的には3までしか数えていないので、小さなお子様の場合は3拍子であると思っていることが多いのですが、3拍目の3がさ〜んって間延びしていると、実際には4拍子になっています。3拍子って難しいですよね。
人間は「1,2,1,2」で歩くので、2拍子や4拍子は体に馴染んでいるのですが、3拍子になると、どうしても3拍目が長くなってしまう生徒さんがいらっしゃいます。3拍目を数えたらすぐに次の1拍目がやってくることを、根気よく覚えていくしかありません。生徒さんが慣れるまでは、保護者の方が横について「1,2,3,1,2,3」と一緒にカウントするのがよいでしょう。ただし、生徒さんも一緒に声に出して数えることが大切です。
いつまでも生徒さんの横で数えてあげていると、生徒さん自身が数えることをやめてしまいますからオススメできません。「自分で数えながら弾く」ことが重要なのであって、正しくリズムを理解できているかの目安になりますので、数えながら練習を徹底しましょう。
生徒の皆さんは、ピアノ学習を進めるに当たって「目標」を持っているでしょうか?ただ「頑張ります」と言うよりも、何かしらの目標を立てると、練習もさらに頑張れると思います。
目標を持った生徒さんの頑張りは、すごいなぁと思うことがあります。初級レベルが終了したらジブリの曲が弾けることを知った生徒さん、早くジブリに進みたくて、最近の頑張りがすごいのです。たくさん練習していることがよくわかります。また、ショパンの曲が弾けるようになりたいと思っている生徒さんは、今、表現力を養うレッスン中。遅くにピアノ学習を始められたので、結構なスパルタレッスンでしたが、今では音もリズムも完璧です。つい先日も「よく怖いレッスンについてきたよね〜」なんてお話をしたところ。
目標は大げさなものでなくていいと思うのです。今年中にテキストを終了させる、とか、1週間で1曲仕上げる、とか。 音読み大会だってその一つ。今まで「音符カードやっておいてよ」と言っても、進んで学習してくれなかったのに、タイムを計るようになったらお家で学習してきてくれるようになった生徒さんが何人も。「絶対に合格する」と言う強い意思が感じられます。
ピアノだけに限らず、学校の学習にも共通して言えることだと思います。次のテストで〇〇点以上取る、などの具体的な目標があると、自ずとやるべきことがわかってくると思うのですが・・・。ピアノを練習する上で具体的な目標がない生徒さんは、ちょっと頑張ったらできる目標を立ててみてはどうでしょうか?
目標を持った生徒さんの頑張りは、すごいなぁと思うことがあります。初級レベルが終了したらジブリの曲が弾けることを知った生徒さん、早くジブリに進みたくて、最近の頑張りがすごいのです。たくさん練習していることがよくわかります。また、ショパンの曲が弾けるようになりたいと思っている生徒さんは、今、表現力を養うレッスン中。遅くにピアノ学習を始められたので、結構なスパルタレッスンでしたが、今では音もリズムも完璧です。つい先日も「よく怖いレッスンについてきたよね〜」なんてお話をしたところ。
目標は大げさなものでなくていいと思うのです。今年中にテキストを終了させる、とか、1週間で1曲仕上げる、とか。 音読み大会だってその一つ。今まで「音符カードやっておいてよ」と言っても、進んで学習してくれなかったのに、タイムを計るようになったらお家で学習してきてくれるようになった生徒さんが何人も。「絶対に合格する」と言う強い意思が感じられます。
ピアノだけに限らず、学校の学習にも共通して言えることだと思います。次のテストで〇〇点以上取る、などの具体的な目標があると、自ずとやるべきことがわかってくると思うのですが・・・。ピアノを練習する上で具体的な目標がない生徒さんは、ちょっと頑張ったらできる目標を立ててみてはどうでしょうか?
最近は、生徒の保護者の方に「ピアノって脳に良いのですよね?」と聞かれることが多くなりました。テレビにもよく出演なさっている脳科学者の澤口先生の影響かな?とも思うのですが、これってただただ習っていても脳に良いわけではありません。
では、脳に良い、脳を使ったピアノの弾き方は?ピアノは、音、リズムなど楽譜の中の情報を目で見て、脳で処理をし、指先に指令を出しています。ペダルを使うようになったら、足にも指令を出していますから、右手・左手・足がそれぞれ違う動きをしていることになります。自分が弾いた音の響きを確かめながら、目では次の音符を追いかけて・・・。この一連の動作は、かなり集中していないとできません。集中するということは脳を使っていますので、脳が鍛えられるということです。
具体的には、どうすれば良いのか?それは、次々に新しい曲をこなすことです。発表会などの曲は別ですが、普段の練習曲を3~4ヶ月かけて弾いているようでは、脳を使っているとは言えません。楽譜を見ながらささっと弾くことが重要なのですから、音読みに時間がかかって、毎回、音を数えているようではダメなのです。鍵盤ばかり見ないで、楽譜を見ながら弾く癖をつけましょう。
お子様に良いピアノというのは、実は大人にも良くて、認知症予防にも良いのです。5本の指を平等に使い、両手がバラバラの動きをし、さらに右脳と左脳の両方を使いますから、お父さん、お母さんにも良いピアノです。最近は、認知症予防のために大人のピアノ学習者も増えましたよね。保護者の方も、ピアノを習ってみませんか?
脳に良いピアノですが、1番大切なことは楽しんで弾くことです。やらされている感が強いとドーパミンが出ないので、効果はありません。楽しみながら練習をしていたら、結果的に脳を使っていた・・・というのが理想的ではないでしょうか?さぁ、今日も楽しく練習練習!
では、脳に良い、脳を使ったピアノの弾き方は?ピアノは、音、リズムなど楽譜の中の情報を目で見て、脳で処理をし、指先に指令を出しています。ペダルを使うようになったら、足にも指令を出していますから、右手・左手・足がそれぞれ違う動きをしていることになります。自分が弾いた音の響きを確かめながら、目では次の音符を追いかけて・・・。この一連の動作は、かなり集中していないとできません。集中するということは脳を使っていますので、脳が鍛えられるということです。
具体的には、どうすれば良いのか?それは、次々に新しい曲をこなすことです。発表会などの曲は別ですが、普段の練習曲を3~4ヶ月かけて弾いているようでは、脳を使っているとは言えません。楽譜を見ながらささっと弾くことが重要なのですから、音読みに時間がかかって、毎回、音を数えているようではダメなのです。鍵盤ばかり見ないで、楽譜を見ながら弾く癖をつけましょう。
お子様に良いピアノというのは、実は大人にも良くて、認知症予防にも良いのです。5本の指を平等に使い、両手がバラバラの動きをし、さらに右脳と左脳の両方を使いますから、お父さん、お母さんにも良いピアノです。最近は、認知症予防のために大人のピアノ学習者も増えましたよね。保護者の方も、ピアノを習ってみませんか?
脳に良いピアノですが、1番大切なことは楽しんで弾くことです。やらされている感が強いとドーパミンが出ないので、効果はありません。楽しみながら練習をしていたら、結果的に脳を使っていた・・・というのが理想的ではないでしょうか?さぁ、今日も楽しく練習練習!
ピアノって練習が必要な習い事です。練習を積めばメキメキと上達をしますが、練習をサボってばかりいたら上達はしません。当たり前の話ですよね。
ピアノが大好きで習い始めて、練習ばかりし過ぎて困ってる・・・なんていうご家庭はそうそうないと思います。1番良い方法は、毎日、歯磨きや食事を取ることと同じで、習慣化してしまうこと。ピアノは練習しなくてはならないものにしてしまえば、そしてそれが普通になっていけばとっても楽に過ごせます。
習慣化するには、習い始めた時から取り組むのが1番です。◯時になったら練習を開始するでもいいですし、◯分練習をするでも、1曲につき◯回弾くでも、何でもいいのです。ただ、毎日取り組むことが大切です。今日は2時間弾くけど、明日から当分弾かないでは、習慣づけができているとは言えません。こうやって毎日の練習を積んでいくと上達も早いので、ピアノが楽しくなり、楽しいから練習が苦ではなくなり、さらに練習をする・・・理想的ですね。
小さい時に習慣づけをしておくと、高学年や中学生・高校生になった時には放っておいても一人でできるようになります。間違っても「練習しておいてね」と言って、隣の部屋で保護者の方がテレビやスマホを触っているということのないようにお願いします。テレビやスマホが楽しいのはお子様も一緒です。練習の間は時間が許す限り、付き添うようにしてあげてください。
ピアノが大好きで習い始めて、練習ばかりし過ぎて困ってる・・・なんていうご家庭はそうそうないと思います。1番良い方法は、毎日、歯磨きや食事を取ることと同じで、習慣化してしまうこと。ピアノは練習しなくてはならないものにしてしまえば、そしてそれが普通になっていけばとっても楽に過ごせます。
習慣化するには、習い始めた時から取り組むのが1番です。◯時になったら練習を開始するでもいいですし、◯分練習をするでも、1曲につき◯回弾くでも、何でもいいのです。ただ、毎日取り組むことが大切です。今日は2時間弾くけど、明日から当分弾かないでは、習慣づけができているとは言えません。こうやって毎日の練習を積んでいくと上達も早いので、ピアノが楽しくなり、楽しいから練習が苦ではなくなり、さらに練習をする・・・理想的ですね。
小さい時に習慣づけをしておくと、高学年や中学生・高校生になった時には放っておいても一人でできるようになります。間違っても「練習しておいてね」と言って、隣の部屋で保護者の方がテレビやスマホを触っているということのないようにお願いします。テレビやスマホが楽しいのはお子様も一緒です。練習の間は時間が許す限り、付き添うようにしてあげてください。