講師から
夏休みも8月に突入です。暑い中、元気に生徒さんたちは通ってきてくださっています。夏風邪を患っている生徒さんも何人か見受けられますが、まずまず元気なようです。体調管理に気をつけて過ごしていきましょう。
さて、ピアノ練習は朝1番練習がオススメなのですが、その理由をご存知でしょうか?ピアノは指先を使います。指を使う事は脳の働きに良いことがわかっていますので、ピアノ練習をする事で、脳が動き出します。ピアノ練習を朝1番にすることで、脳の働きを促してくれて、脳が活発に動くようになるとのこと。普段は、学校に行く前にピアノの練習時間を取る事は難しいかもしれませんが、今はちょうど夏休み。通常よりも時間に余裕がある夏休みなので、朝1番にピアノ練習を取り入れてみてはいかがでしょうか?
もう1つ余談ですが、朝1番にピアノ練習をした後は、算数や数学の計算問題に取りかかるといいと言われています。この話はピアノの先生の間ではよく言われている事ですが、動き出した脳を計算問題を解くことによって、さらに活発にしてくれます。その後の仕事(学習)の効率が良くなるとのことなので、取り組んでみる価値はありそう。1日の時間の中でピアノ練習も学習もやるのであれば、駄目元で取り組んでみてもいいのではないでしょうか?結果がついてくればラッキーな程度に考えておけば、気分も楽です。有意義な夏休みを!
さて、ピアノ練習は朝1番練習がオススメなのですが、その理由をご存知でしょうか?ピアノは指先を使います。指を使う事は脳の働きに良いことがわかっていますので、ピアノ練習をする事で、脳が動き出します。ピアノ練習を朝1番にすることで、脳の働きを促してくれて、脳が活発に動くようになるとのこと。普段は、学校に行く前にピアノの練習時間を取る事は難しいかもしれませんが、今はちょうど夏休み。通常よりも時間に余裕がある夏休みなので、朝1番にピアノ練習を取り入れてみてはいかがでしょうか?
もう1つ余談ですが、朝1番にピアノ練習をした後は、算数や数学の計算問題に取りかかるといいと言われています。この話はピアノの先生の間ではよく言われている事ですが、動き出した脳を計算問題を解くことによって、さらに活発にしてくれます。その後の仕事(学習)の効率が良くなるとのことなので、取り組んでみる価値はありそう。1日の時間の中でピアノ練習も学習もやるのであれば、駄目元で取り組んでみてもいいのではないでしょうか?結果がついてくればラッキーな程度に考えておけば、気分も楽です。有意義な夏休みを!
私の個人的な考えですが、子供って少々の無理は難なくこなします。ただし条件付きですが。限界を決めているのは親(大人)側であって、限界を知らない子供側からすると、突っ走ることができるからです。子供が無理できる条件は、ズバリ親。親の対応次第で子供はいくらでも頑張れます。
この時期、新しい曲に挑戦する中学3年生の合唱コンクールのピアノ伴奏者には、1日2時間のピアノ練習をするように言っています。これ、かなりな無理強いです。高校受験生に対して、勉強と関係のないピアノ練習をするように言う事は、私も心苦しいです。でも、ピアノ講師の立場からすると至って普通。これが受験生の親の立場になると「勉強しなさい。ピアノもしなさい。全てに頑張りなさい」になります。我が家の子供たちも大学生になったので、受験生の親の立場もわかります。
では、子供の立場ではどうでしょうか?「ガンバレ、やりなさい」の押し付けだけでは、子供は壊れてしまいます。壊れると言うのは、精神的に病んでしまうこと。実際によくある話ですが、塾を2つ3つと掛け持ちをしていても、こなせている子供と、どこか病んでしまう子供の違いは親のフォローの違いです。「頑張っているね」の一言があるかないか。認めてくれる、見てくれている親がいるという安心感が、子供の安定につながります。
私もピアノ講師の立場で、生徒さんにはフォローをしているつもりです。しかし、1番長い時間を過ごすのは家族、親。親に認めてもらうことで、無理もできるし頑張れます。お子様の頑張り、どうか見てあげて。
この時期、新しい曲に挑戦する中学3年生の合唱コンクールのピアノ伴奏者には、1日2時間のピアノ練習をするように言っています。これ、かなりな無理強いです。高校受験生に対して、勉強と関係のないピアノ練習をするように言う事は、私も心苦しいです。でも、ピアノ講師の立場からすると至って普通。これが受験生の親の立場になると「勉強しなさい。ピアノもしなさい。全てに頑張りなさい」になります。我が家の子供たちも大学生になったので、受験生の親の立場もわかります。
では、子供の立場ではどうでしょうか?「ガンバレ、やりなさい」の押し付けだけでは、子供は壊れてしまいます。壊れると言うのは、精神的に病んでしまうこと。実際によくある話ですが、塾を2つ3つと掛け持ちをしていても、こなせている子供と、どこか病んでしまう子供の違いは親のフォローの違いです。「頑張っているね」の一言があるかないか。認めてくれる、見てくれている親がいるという安心感が、子供の安定につながります。
私もピアノ講師の立場で、生徒さんにはフォローをしているつもりです。しかし、1番長い時間を過ごすのは家族、親。親に認めてもらうことで、無理もできるし頑張れます。お子様の頑張り、どうか見てあげて。
 小さな生徒さんに多いのですが、ピアノの鍵盤を押さえるときに、腕からの力に頼っていると、写真のような指で弾いていることがあります。第一関節が内側に曲がっていますよね?この弾き方、1番ダメな弾き方です。もちろん、鍵盤に触れる指先には多少の力が必要ですが、押さえつけるような強い力は必要ありません。
小さな生徒さんに多いのですが、ピアノの鍵盤を押さえるときに、腕からの力に頼っていると、写真のような指で弾いていることがあります。第一関節が内側に曲がっていますよね?この弾き方、1番ダメな弾き方です。もちろん、鍵盤に触れる指先には多少の力が必要ですが、押さえつけるような強い力は必要ありません。小さな生徒さん(小学3~4年生くらいまで)の場合、指の関節も手の筋肉も未発達なため、思うように大きな音が出ません。大きな音を出すことを優先させるのではなく、綺麗な指の形で弾くことを優先させましょう。変な指の形が定着してしまうと、綺麗な音が出せなくなりますし、正しい形に直すことが困難になってしまいます。付き添い練習をしてくださっている保護者の方は、指の形をチェックしていただき、必要な声かけをお願いいたします。
どの程度の指の力が必要なのか、目安としては、実際のピアノではなく、机やテーブルでピアノを弾く時の指の形を作ってみるとわかりやすいと思います。ピアノの鍵盤を弾いて練習していると、どうしても自分が出すピアノの音の大きさが気になってしまい、音を出すことに意識が行きがちです。机やテーブル相手だと音は出ませんから、指の形だけに集中できます。机やテーブルをピアノに見立てて指を動かした時、第一関節の状態を観察してみましょう。正しい指の形で動かしている時の指の力が必要な指の力になります。やってみるとわかりますが、そんなに力を込めなくてもスムーズに動かすことができるはずです。
指がしっかり作られてきたら、綺麗な響きのある大きな音は出せるようになってきます。年齢とともに関節も筋肉も発達してきますので、心配はいりません。綺麗な音を出すための第一歩は指作り。力を抜いて楽に弾きましょう。
中学生になると、1年に1度行われる「合唱コンクール」。練馬区の場合は、練馬駅前にある練馬文化センターで行われることが多いです。ピアノを習っている生徒さんの中には、合唱コンクールでのピアノ伴奏に憧れる人も多く、自分の子供にピアノ伴奏をしてもらいたい・させたい、と考える保護者も多いです。
ピアノ伴奏者は大抵の場合、オーデションで決定します。学校やクラスによっては、ピアノを弾ける人や弾きたいと思っている人が少なくて、オーデションが行われないこともあるようですが、ごく稀です。普通はオーデションです。3人の中から2名が選ばれることもあれば、多いクラスになると、5~6人の中から選ばれることも。ピアノを習っている人が多いのも事実で、生徒さんたちは壮絶な戦いをして、ピアノ伴奏者の座を勝ち取って来ます。
毎年、何人もの生徒さんがオーデションでピアノ伴奏を勝ち取って来ますが、共通することは、日頃の練習をきちんとしていること。テスト期間中など、練習ができない日が続くこともありますが、それ以外ではきちんと練習をされています。1週間、1度もピアノに触らずにレッスンに来ることはありません。たくさんの時間は取れなくても、時間を見つけて練習に励んでいます。
先日も保護者の方から、ピアノ伴奏を目指したい、と連絡をいただきました。保護者の方の希望はわかりますが、実際に練習をするのはお子様です。きつい言い方になりますが、させたいのであれば、日頃の練習もさせなければ無理です。オーデションの前だけ練習に励んでも、コツコツと頑張っている生徒さんには叶いません。ペダルや曲の表現力など、日頃の練習が重要になってきます。学校での活躍を目指すのであれば、日頃の練習、日頃のレッスンを大切にして欲しいと思います。
ピアノ伴奏者は大抵の場合、オーデションで決定します。学校やクラスによっては、ピアノを弾ける人や弾きたいと思っている人が少なくて、オーデションが行われないこともあるようですが、ごく稀です。普通はオーデションです。3人の中から2名が選ばれることもあれば、多いクラスになると、5~6人の中から選ばれることも。ピアノを習っている人が多いのも事実で、生徒さんたちは壮絶な戦いをして、ピアノ伴奏者の座を勝ち取って来ます。
毎年、何人もの生徒さんがオーデションでピアノ伴奏を勝ち取って来ますが、共通することは、日頃の練習をきちんとしていること。テスト期間中など、練習ができない日が続くこともありますが、それ以外ではきちんと練習をされています。1週間、1度もピアノに触らずにレッスンに来ることはありません。たくさんの時間は取れなくても、時間を見つけて練習に励んでいます。
先日も保護者の方から、ピアノ伴奏を目指したい、と連絡をいただきました。保護者の方の希望はわかりますが、実際に練習をするのはお子様です。きつい言い方になりますが、させたいのであれば、日頃の練習もさせなければ無理です。オーデションの前だけ練習に励んでも、コツコツと頑張っている生徒さんには叶いません。ペダルや曲の表現力など、日頃の練習が重要になってきます。学校での活躍を目指すのであれば、日頃の練習、日頃のレッスンを大切にして欲しいと思います。
 自由に手を動かしてピアノを弾くためには、自分とピアノとの距離、椅子の高さなど、気をつけるべきことがたくさんあります。それらは、体の大きさや身長によって違ってきますので、一人一人、微妙に違ってきます。
自由に手を動かしてピアノを弾くためには、自分とピアノとの距離、椅子の高さなど、気をつけるべきことがたくさんあります。それらは、体の大きさや身長によって違ってきますので、一人一人、微妙に違ってきます。ピアノを弾く時の手の形にも注意が必要ですが、鍵盤に手を乗せた時の手首の位置にも注意が必要です。わかりづらいかもしれませんが、写真の生徒さんの手首の位置は、ピアノの鍵盤よりも下がっています。ピアノの黒い部分に寄りかかるようにして手を置いていると、手首は下がってしまいます。親指(1番の指)がべチャンと、鍵盤に触りすぎると手首が下がります。親指が鍵盤に触れる部分は、ほかの指と同様にほんの少しだけです。
座る椅子の高さによっても手首の位置が変わってきます。低い椅子に座ってピアノを弾くと、手首も下がりますので、ちょうど良い高さの椅子に座るようにしましょう。真横から見た時に、ピアノの白い鍵盤と腕の位置が同じ高さになるくらいが、適切な状態だと言われています。ピアノを弾く本人が確認することは難しいので、保護者の方が真横から見ていただいて確認をお願いします。
体にストレスをかけたままでのピアノ演奏は、上手に弾けるものも上手に弾けなくなります。演奏する鍵盤の音域が広がっていくと、腕を自由に動かして弾かなければなりません。ピアノとの距離も重要になってきます。何気なく座って弾いているピアノですが、気持ちよく弾ける距離は自分にしかわかりません。自分に最適な距離を時々は意識してみると良いでしょう。
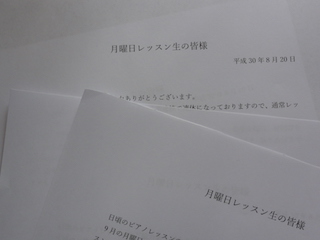 月曜日の生徒さん限定でお手紙を配布しました。振替レッスンをされている生徒さんもいらっしゃるので、全員には行き渡っていませんが、順にお渡しする予定です。
月曜日の生徒さん限定でお手紙を配布しました。振替レッスンをされている生徒さんもいらっしゃるので、全員には行き渡っていませんが、順にお渡しする予定です。9月のレッスン予定についてのお便りなのですが、月曜日はハッピーマンデーの関係で、9月の通常レッスンは2回となります。年間のレッスン回数はどの曜日にレッスンを受けていただいても、年間42回レッスンの設定ですので、多い少ないはありませんが、月曜日は秋以降、祝日が多くなりますので、3回目のレッスンを違う曜日でお取りいただきたいと考えています。その旨を書いたお手紙なので、月曜日限定になっています。
お手紙にも書いてありますが、他の曜日は通常レッスンをしておりますので、思うような時間帯がお取りできない可能性もあります。第2・第3希望まで申し出ていただくと助かります。また、中学生以上の生徒さんには、お手紙と同時に直接お話もさせていただいています。自分の予定がわかっている場合は、早めに振替を申し込んで下さい。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
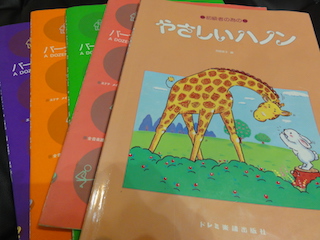 「こっちやってくるの忘れた」と、毎週のように誰かが弾いてこない、ハノンやバーナムのテクニック教材。他の練習曲も弾いていないのなら、練習自体をやっていないと言うことなので、テクニック教材を弾いていないのも理解できます。しかし、練習曲は練習ができているのに、テクニック教材だけを忘れた・・・と言うのは、ちょっと理解に苦しみます。それ、絶対に確信犯でしょ?
「こっちやってくるの忘れた」と、毎週のように誰かが弾いてこない、ハノンやバーナムのテクニック教材。他の練習曲も弾いていないのなら、練習自体をやっていないと言うことなので、テクニック教材を弾いていないのも理解できます。しかし、練習曲は練習ができているのに、テクニック教材だけを忘れた・・・と言うのは、ちょっと理解に苦しみます。それ、絶対に確信犯でしょ?テクニック教材って、つまらない・楽しくない・面倒臭い・・・って思いませんか?正解です!私もそう思います。私も好きじゃない。そりゃぁ、曲集弾いている方が楽しいです。でも、その曲集を上手に、素敵に弾くための1番大切な練習がテクニック教材なのです。簡単な曲を弾いている間はよくわからないかもしれません。少し難しくなって、トリルや装飾音符、32分音符などを弾くようになると、しっかりした指と表現力が必要になってきます。テクニックは1日2日で身につくものではありませんので、コツコツ練習が大切。そのために、生徒の皆さんにはテクニック教材を学習してもらっています。
テクニック教材は、体育の授業で言うなら準備体操のようなもの。レッスンでも、必ずテクニック教材から始めます。ですから自宅練習でも、後回しにせずに最初に練習をしてしまうと良いです。そうすれば「忘れた」なんてことにもなりません。せっかくのピアノ学習、テクニックを身につけて素敵にピアノを弾いていきましょう。