講師から
では、ゆっくり練習からだんだん速くしていくタイミングは、どういう 時がいいでしょうか?もちろん、ゆっくりの速さで弾けるようになってからなのですが、じゃぁ1回弾けたらそれでいいのか・・・?というと、そうではありま せん。2〜3回弾けるようようになっただけでは、ひょっとしたら「たまたま」の2〜3回かもしれません。ちょっと意地の悪い見方ですが、その曲の演奏が 完全に自分のものになっていないと、速い速さでは弾けないものです。目安的には、私がよく言う「5回練習」の5回弾けるようになっていたら、自分の演奏に なっていると考えていいと思います。5回連続して間違いがなく弾けるようになったら、少しづつその曲の速さに近づけていきましょう。自分の演奏の向上を 目指して先に先に進んで欲しいと思います。ただ、私から「まだダメだよ」と、生徒さんに先に伝える場合もあります。
今回、ポピュラー曲を練習中の 生徒さん。ちょうど写真に載っている8小節の部分は「1と2とお、3と4と」と、お を使って数えるような細かなリズム曲です。これがまた難しい。リズムも 細かくてタイでも結ばれていて、よく知っているポピュラー曲。よく知ったポピュラー曲はメロディーラインが頭の中でわかっているので、ついついそのメロディー ラインを追ってしまいがち。YouTubeなどでも聴けることから手軽に練習ができる良い面がありますが、楽譜通りに演奏をしようと思えば丁寧な練習が必要に なってきます。細かなリズムであれば尚更です。この細かなリズムをゆっくりで何とか弾けるようになってきた生徒さん。でも、弾けたり弾けなかったり・・・の 繰り返しです。この状態では、まだこの部分のリズムが自分のものになっていませんから、もう少しゆっくり練習で自分のものにする必要があります。生徒さん 的には早く速い速さでの練習がしたいところ(だと思う)。でもここで焦ってしまうとまたやり直しになってしまいます。生徒さんには「まだ速く弾いちゃダメ だよ。今じゃないよ。まだだよ」と、釘を刺しておきました(笑)日頃は「やってきてよ〜」と、先に先に進んでもらうことも多いのですが、より丁寧な練習 が必要な箇所とそうでない箇所の見極めができるようになると良いと思います。取りにくいリズム・細かな音ほど、丁寧な練習が必要です。まず先に、 ゆっくり練習を自分のものにしてから進めていくようにしていきましょう。
曲の速さについては、生徒さんによっては、ごく稀に、 曲の途中から速くなったり、遅くなったりなど一定の速さが保てない生徒さんもいらっしゃいます。もちろん仕上がりがそのような状態ではいけないので、 メトロノームに合わせた練習を取り入れることになります。この場合のメトロノーム練習は、一定の速さで弾けるようにするためのメトロノーム練習になり ます。メトロノームで強制的に一定の速さを保てるように修正していきます。この練習を継続していくと、体が速さを覚えていくので、メトロノームがなく ても一定の速さで弾けるようになります。この状態になれば本番でも安心です。どうしても一定の速さが保てなかった生徒さんにメトロノーム練習を 取り入れてもらった結果、レッスンではメトロノームがなくても一定の速さで弾けるようになっていました。じゃ、もうメトロノーム練習はお終いね・・・・ としたいところですが、生徒さんへは「メトロノーム練習は継続しておいてね」と、指示を出しました。ほぼほぼ完成しているステップ曲ですが、メトロノーム 練習が続くことに『?』だった生徒さん。それはそうですね。ここからは本番までの2ヶ月の期間を崩さないためのメトロノーム練習になります。まだ低学年の 生徒さんですが「弾けている曲の速さを崩さないためのメトロノーム練習になりますよ」と、説明をさせてもらいました。いまメトロノームを取り除いて しまうと崩れる可能性が高いと判断した結果です。実はこちらの生徒さん、今までの練習曲でも、曲の途中から速く速くなってしまう癖をお持ちの生徒さん です。ピアノを楽しんで演奏していらっしゃるので、弾きたい気持ちが焦らせちゃうのかな?私の説明に納得をしてくれたようでした。
どの生徒さんも あまり好きでないメトロノーム練習ですが、そのメトロノーム練習にも目的が違う練習が存在します。あっちにいったりこっちにいったりしている曲の速さを 強制するためのメトロノーム練習(大抵はこちらの目的で使うことが多いです)と、今回の生徒さんのケースのように、弾けるようになっているけれど本番 までの期間に崩さないためのメトロノーム練習。ステップや合唱コンクール伴奏など、本番が控えている生徒さんに用いることが多い練習です。どちらに しても、何故、その練習が必要なのか、自分が納得していないと練習は続けることが難しいです。押し付けでない練習の提案ができるように気をつけていきたい と思っています。
「レッスンでは子供を褒めないでください。厳しく伝えてください」と、1通のメールが届きました。小学校低学年のお母様からのメールです。ピアノの練習を
しない・言うことを聞かなくなった・・・と、書いてありました。夏休みに入って自由な時間が増えたことで、遊びの時間ばかりになってしまったのかも
しれません。レッスンの前日にメールが届いたので、生徒さんとお話をしてみます・・・と返事をして次の日のレッスンを迎えました。
私のピアノ レッスンは、特別に褒めるレッスンをしているわけではありません。良くできていれば褒めますし、できていない場合はダメ出しもします。いたって普通の レッスン(のつもり)。ただ、春からレッスンを始めた生徒さんですから、内容がまだ簡単で、はっきり言って練習をしていなくても弾けてしまう内容です。 できていれば合格にはなりますから、1曲づつ進んでいきます。きっと練習をしなくても1曲づつ進んでいくので、生徒さんは簡単に感じてしまったのかも しれません。ただ、簡単に感じるのは最初だけで、音読みやリズムなどを理解していかなければ、ゆくゆくは辛くできなくなっていきます。お母様はピアノを 弾かれますので、ピアノには練習が必要なこともわかってくださっています。今の最初の段階でピアノ練習の癖をつけておくことが重要なこともわかって くださっているのだと思います。さぁ、どうしましょう・・・?
生徒さんは小学校の低学年ですが、丁寧にお話をしてわかってもらう必要が あると思いました。私の考えや思いになりますが、ピアノのレッスンにはピアノの練習が必要なこと、お父さん・お母さんの言うことは聞くこと、学校の宿題は 必ずすることを、お話しさせていただきました。親から言われることは、わかっていても素直に聞けないことが、よその人や親以外の人から言われたり注意を 受けたりすると、案外素直に受け入れられることってあると思います。そうやって、きちんとできた時には親や周りが褒める、できていなければ注意をする・・・ の繰り返しで学んでいくと思うのですが、どうでしょうか?実はこちらの生徒さん、春からお父様が海外に単身赴任になり、お母様と二人での生活が続いて います。きっとお母様も一人で大変な思いをされているでしょうし、生徒さんも多少のストレスもあるかもしれません。普通に生活をしていても友達関係やら 学校関係などでストレスを抱えるもの。そんな中のSOSメールでした。困ったことを相談してくれたお母様に感謝です。
私はそこらへんの?ピアノの 先生なので、何ができるわけではありません。しかし、1週間に1度、生徒さんの様子を見ている中での生徒さんの様子や変化を感じることもあります。時には ピアノを弾かずに生徒さんとお話をすることもありますし、悩みを聞くこともあります。それで生徒さんの心が落ち着くのであれば、1回や2回のピアノを 弾かない時間も無駄にはならないはず。お子様の様子で気になることなどありましたら、声をかけていただければ・・・と思います。保護者の方も一人で悩む ことなく、皆で見守る体制を築いていくようにしていきましょう。
私のピアノ レッスンは、特別に褒めるレッスンをしているわけではありません。良くできていれば褒めますし、できていない場合はダメ出しもします。いたって普通の レッスン(のつもり)。ただ、春からレッスンを始めた生徒さんですから、内容がまだ簡単で、はっきり言って練習をしていなくても弾けてしまう内容です。 できていれば合格にはなりますから、1曲づつ進んでいきます。きっと練習をしなくても1曲づつ進んでいくので、生徒さんは簡単に感じてしまったのかも しれません。ただ、簡単に感じるのは最初だけで、音読みやリズムなどを理解していかなければ、ゆくゆくは辛くできなくなっていきます。お母様はピアノを 弾かれますので、ピアノには練習が必要なこともわかってくださっています。今の最初の段階でピアノ練習の癖をつけておくことが重要なこともわかって くださっているのだと思います。さぁ、どうしましょう・・・?
生徒さんは小学校の低学年ですが、丁寧にお話をしてわかってもらう必要が あると思いました。私の考えや思いになりますが、ピアノのレッスンにはピアノの練習が必要なこと、お父さん・お母さんの言うことは聞くこと、学校の宿題は 必ずすることを、お話しさせていただきました。親から言われることは、わかっていても素直に聞けないことが、よその人や親以外の人から言われたり注意を 受けたりすると、案外素直に受け入れられることってあると思います。そうやって、きちんとできた時には親や周りが褒める、できていなければ注意をする・・・ の繰り返しで学んでいくと思うのですが、どうでしょうか?実はこちらの生徒さん、春からお父様が海外に単身赴任になり、お母様と二人での生活が続いて います。きっとお母様も一人で大変な思いをされているでしょうし、生徒さんも多少のストレスもあるかもしれません。普通に生活をしていても友達関係やら 学校関係などでストレスを抱えるもの。そんな中のSOSメールでした。困ったことを相談してくれたお母様に感謝です。
私はそこらへんの?ピアノの 先生なので、何ができるわけではありません。しかし、1週間に1度、生徒さんの様子を見ている中での生徒さんの様子や変化を感じることもあります。時には ピアノを弾かずに生徒さんとお話をすることもありますし、悩みを聞くこともあります。それで生徒さんの心が落ち着くのであれば、1回や2回のピアノを 弾かない時間も無駄にはならないはず。お子様の様子で気になることなどありましたら、声をかけていただければ・・・と思います。保護者の方も一人で悩む ことなく、皆で見守る体制を築いていくようにしていきましょう。
夏休みに入って2週間ほどが過ぎ去った頃でしょうか?夏休みの宿題は計画的に済んでいますか?さて、ピアノのレッスンですが、ピアノは一部の大人の
生徒さんや大学生の生徒さんを除いて、毎週決まった曜日のレッスンです。基本的には夏休みなどの長期の休み期間も、学校がある時と同じ曜日・時間での
レッスンを行っています。・・・・が、ここ最近、レッスンを忘れてしまう生徒さんがちらほらいらっしゃいます。
特に多く感じるのは、中学生 以上の生徒さんたち。「曜日感覚がなくて・・・」とおっしゃる生徒さんもいらっしゃいます。確かにそうかもしれません。部活動によっては、夏休みの 期間、活動の自粛が続いている部活もあるようです。そうなると、ぶっちゃけ、毎日が祝日のようなもの(?)毎日、朝起きて家の中で過ごして、夜になったら 寝て・・・を繰り返していると、「今日は何日?何曜日?」となってしまうのかもしれません。今年は特にオリンピックの関係で、カレンダーの祝日が移動 したり、お勤めの保護者の方もリモートワークでおうちにいらっしゃったりなど、いつもの夏休みとは違う夏休みになっているご家庭もあるかと思います。 今一度、朝起きたなら、その日の予定を確認してもらえると嬉しいです。
先日も、夜遅いレッスン生の生徒さんがいらっしゃらないので、ソワソワ しながら時計と睨めっこ。ちょうど電車の切りつけ事件などもあったばっかりで、学校帰りに事件に巻き込まれているかも・・・と思いながらメールを送っても 返信がありません。自宅に連絡を入れてみたところ、「忘れてました」とのこと。いや〜、事件や事故ではなかったことに安堵し、結局、笑い話で終わったの ですが、やはり夜遅い時間のレッスンだけに心配になります。中学生・高校生の大きな生徒さんであっても、ピアノの曜日の確認やその日の予定の確認などを、 保護者の方も一緒に一言添えていただくだけで、忘れることは防げるのではないかと思います。出席カードやレッスンノートなどでレッスン予定を確認して いただき、都合が悪いようでしたらお休みや振替連絡を早めに入れていただけると、対応ができますので確認をお願いしたいです。くれぐれも「忘れていました」 と言うことのないようにお願いいたします。
特に多く感じるのは、中学生 以上の生徒さんたち。「曜日感覚がなくて・・・」とおっしゃる生徒さんもいらっしゃいます。確かにそうかもしれません。部活動によっては、夏休みの 期間、活動の自粛が続いている部活もあるようです。そうなると、ぶっちゃけ、毎日が祝日のようなもの(?)毎日、朝起きて家の中で過ごして、夜になったら 寝て・・・を繰り返していると、「今日は何日?何曜日?」となってしまうのかもしれません。今年は特にオリンピックの関係で、カレンダーの祝日が移動 したり、お勤めの保護者の方もリモートワークでおうちにいらっしゃったりなど、いつもの夏休みとは違う夏休みになっているご家庭もあるかと思います。 今一度、朝起きたなら、その日の予定を確認してもらえると嬉しいです。
先日も、夜遅いレッスン生の生徒さんがいらっしゃらないので、ソワソワ しながら時計と睨めっこ。ちょうど電車の切りつけ事件などもあったばっかりで、学校帰りに事件に巻き込まれているかも・・・と思いながらメールを送っても 返信がありません。自宅に連絡を入れてみたところ、「忘れてました」とのこと。いや〜、事件や事故ではなかったことに安堵し、結局、笑い話で終わったの ですが、やはり夜遅い時間のレッスンだけに心配になります。中学生・高校生の大きな生徒さんであっても、ピアノの曜日の確認やその日の予定の確認などを、 保護者の方も一緒に一言添えていただくだけで、忘れることは防げるのではないかと思います。出席カードやレッスンノートなどでレッスン予定を確認して いただき、都合が悪いようでしたらお休みや振替連絡を早めに入れていただけると、対応ができますので確認をお願いしたいです。くれぐれも「忘れていました」 と言うことのないようにお願いいたします。
この曲を演奏するのは未就学児の生徒さん。「曲を 歌う」ことをわかってもらうために、実際に歌詞を歌ってみました。声に出して歌ってみると、伴奏は関係なくメロディーだけを歌うことになりますから、曲が はっきりしてきます。それと同時に、歌い出しの言葉の入れ方も「わ〜たっしゃ・・・」「じょ〜おっずに・・・」といった感じで「〜」のちょっとした間を 感じながら歌うことに気がつくはず。このホンのちょっとした間を、ピアノを演奏する時にも感じてもらえると、メロディーラインがはっきりとしてくる はず。これは時間で測れるものではないので感覚的なものになります。ピアノって、こんな感覚的なことが多くあります。何秒とかの数字的なことではないので 難しいです。
ピアノのレッスン中にも、よく大きな生徒さんには「もっと歌って」とよく言い表しますが、はっきり言って、ピアノでは 歌えません。音が鳴るだけ。「もっと歌って」と言うことは、「表情をつけて」ということ。文章を読む時にも、機械的にダラダラと読む場合と、抑揚を つけて読む場合では違うと思います。ピアノ演奏もそれと一緒。どのように歌って弾いたらよいのかわからない時には、声に出してそのメロディーを歌ったり 歌詞を歌ってみると良くわかると思います。少し難しい話になってしまいましたが、今回の「やまのおんがくか」の曲の場合は、生徒さんと一緒に歌って 曲の楽しさを感じることで、少しはメロディーの出し方がわかってもらえたかなぁ?伝えるって難しい・・・。私もまだまだですね・・・。
加線の音符を素早く読むためには、いつも言っていますが「だんご読み」がいいです。だんご読みとは、線の音符を 1つ飛ばしに読んでいく読み方。そのためには、まずは写真に載っている4つの音がパッとわからなければ読めません。この4つの音、すぐに何の音かわかり ますか?ト音記号のド、ヘ音記号のドの音は、皆さんすぐにわかります。問題は残りの2つ。先日も加線の音に挑戦中の生徒さんに、この4つの音のカードだけを 見せて読んでもらったところ・・・・。ヘ音記号のミ、ト音記号のラがパッと出てきませんでした。だんご読みは、この音がパッとわかっていないと読むことが できませんから、この音は基本の音になります。まずは、この4つの音、2つのドの音についてはわかっているので、実質、残り2つの音を覚えるようにしましょう。
闇雲に音符カードを並べて読んでいっても構いませんが、やはり早く読める技やコツがあるものです。たくさんの音が並ぶ楽譜の曲を演奏する上では、 1つ1つの音を順番に読んでいくよりも、ト音記号・ヘ音記号それぞれのだんご読みができるようになっていると、それだけ早く音に変換できます。効率の良い 練習ができていきますから、1曲の曲の仕上がりも早くなります。曲の仕上がりが早くなると次々に演奏ができるようになるので、ピアノが楽しくなります。 ぜひ、楽しいピアノを目指して、だんご読みができるようにしていきましょう。基本の4つの音(実質2つ)をまずはわかるようにしていきましょう。
 9月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さんたちのレッスンが続いています。今回参加される生徒さんたちは、どの生徒さんたちも曲の仕上がりが早く、
今すぐにでも舞台に立っても良さそうな生徒さんばかり。それはとても良いことではあるのですが、どうせなら9月の本番当日に1番良い演奏状態に持って
いきたいところ。良くできているのは今じゃなくて良いのです。かと言って、まだまだ全然弾けない・・・・と言う状態でもダメで・・・。どう調整を
していくか?難しいところ。
9月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さんたちのレッスンが続いています。今回参加される生徒さんたちは、どの生徒さんたちも曲の仕上がりが早く、
今すぐにでも舞台に立っても良さそうな生徒さんばかり。それはとても良いことではあるのですが、どうせなら9月の本番当日に1番良い演奏状態に持って
いきたいところ。良くできているのは今じゃなくて良いのです。かと言って、まだまだ全然弾けない・・・・と言う状態でもダメで・・・。どう調整を
していくか?難しいところ。よくスポーツ選手、テレビなどでは水泳の選手がインタビューで答えているのを聞いたのですが「本番で1番良い タイムが出るように体を調整していきたいです」と、耳にしました。あ〜、ピアノの演奏も同じだな・・・と思いました。舞台に立つ本番が1番良い演奏になって 欲しいと思います。そのためには水泳選手と同じで、演奏を調整していかなければなりません。これ、結構難しいです。
今、上手に演奏をしている 生徒さんたちへは「一生懸命に練習をしなくていいからね」と伝えています。ピアノの先生が「練習をしなくていい」ってどういうこと?って感じですが、 本番まで1ヶ月もあるので、今は軽く流すくらいでちょうど良いと思っています。演奏以外のお辞儀の練習や椅子への座り方、落ち着いて膝から始める演奏 など、他にも気をつけることがたくさんありますから、演奏以外のことがきちんとできるようにしていきましょう。そろそろ暗譜の練習にも取り掛かると いいでしょう。今、完璧でなくても良いので(完璧でない方が良いです。今が完璧だと落ちていくだけですから)ミスしても落ち込まないで練習を重ねて いきましょう。少しづつ少しづつ上昇していくように、調整していきたいですね。余裕のある生徒さんは、普段のテキスト曲の 練習もしていくとよいでしょう。目指すのは9月のステップです。大きな気持ちで練習を!
生徒さんの今の状況は、あやふやな暗譜になってしまって います。弾き直しをしなくていいように完全に正しいものを覚える必要があるのですが、どうする!?正しく弾けたり弾けなかったりが悪いので、今は、楽譜を 睨みつけて楽譜を見ながら弾く必要があります。ここはレ、ここはファ と言った具合に、今、弾いてい箇所が何の音であるのかを頭の中に入れて欲しいのです。 そのために睨みつけて演奏をします。暗譜をして演奏をしている時の頭の中の状態は、「今、楽譜のこのあたりを弾いている」みたいな感じで、頭の中に 楽譜が出てくる状態です。その頭の中の楽譜を思い出しながら演奏をしていますので、頭の中の楽譜があやふやでは演奏もあやふやです。正しい楽譜が 頭の中に出てくるようにするためには、自分の目で、弾いている箇所を見ながら正しい演奏を重ねるしかありません。
何となく弾けるようになって きたから・・・と、楽譜を見ないで正しかったり正しくなかったりの演奏を繰り返していると、本番で正しく弾けた時は良いのですが、もし、間違って しまったら、小さな生徒さんであれば特に弾き直しをしてしまうでしょう。私のような図太さが備わっていれば、知らん顔してそのまま続けるのですが、 間違えたことをそのままにできない良さを持っている小さな生徒さん。本番でそうならないために、本番までの時間に余裕のある今だから、楽譜を睨みつけて 完璧な楽譜を頭の中に入れてしまいましょう。今、しっかりと楽譜を見ての練習を続けましょう。
 未就学児さんの頃からピアノ学習を始めていると、小学校低学年の頃には、楽譜にペダル記号が出てくるようになります。それだけ難しい曲に進んできたという
証拠なのですが、身長が高くない生徒さんのペダル学習は、ペダル付き足台が必要になります。教室にはペダル付き足台を設置していますが、自宅にもペダルつき足台を
用意していただく必要があるため、ペダル学習の条件は足台の用意ができる生徒さん限定になります。
未就学児さんの頃からピアノ学習を始めていると、小学校低学年の頃には、楽譜にペダル記号が出てくるようになります。それだけ難しい曲に進んできたという
証拠なのですが、身長が高くない生徒さんのペダル学習は、ペダル付き足台が必要になります。教室にはペダル付き足台を設置していますが、自宅にもペダルつき足台を
用意していただく必要があるため、ペダル学習の条件は足台の用意ができる生徒さん限定になります。最近は、遅いピアノ学習の始まりでも、 毎日の練習時間が多い生徒さんもいらっしゃって、そう言う場合は、ピアノ学習歴が短くてもテキストの進度が早くなります。そうすると、テキストにペダル 記号が出てくるようになりますので、身長を見ながらペダル付き足台が必要かどうかを見極めることになります。ただ、スタートが遅いピアノ学習の生徒さんの 注意点は、テキストの進度のわりに指が出来上がっていないこと。音読みやリズムの学習が進んでいき、テキストがスラスラ弾けるようになっていくと、テキスト の進み具合は早いのですが、指がテキストの曲に見合っていない状況が生まれます。楽譜は正しく読めるけれど、音が出来上がっていない状態です。 例えば、芯のある音が出ない、指がふにゃふにゃ、音色が乏しいなど。これらは何年もかかって少しづつ積み上げていくものなので、そう簡単には習得する ことができません。ある程度のしっかりした音を出せる生徒さんでないと、ペダル学習に進むことは難しくなります。
よく思い違いをされる生徒さんも いらっしゃるのですが、ペダルは演奏力を補うものではありません。80を100にするものではありません。100のものを200にするのがペダルの 役割です。音もしっかりとした音が出せて、読譜力もありスラスラ弾けるものを、更に素晴らしい演奏にするために踏むペダルです。補うのではなく、更に プラスにする役割を担っています。ですから、いくらペダルを踏める読譜力があっても、指が出来上がっていなければペダル学習には進めません。その場合は、 まず指を作る作業を優先させることになります。生徒さんお一人お一人の状況を見て、何が必要なのか、どういった提案ができるのかを考えて提示させて もらっていますが、最終的に決定するのは生徒さんと保護者です。何人かの生徒さんへは、ペダル学習の提案をさせてもらっていますが、補うペダルでは ないことを頭の中に入れて学習を進めて欲しいと思います。
教室では音符カード読みを通して音読みをすることを 重視していますので、特に最近の入会の生徒さんたちは音読みができています。写真の生徒さんはピアノ学習を始めて2ヶ月目の、まだまだ新米の生徒さん。 未就学児の生徒さんで、2ヶ月目にして両手で弾く曲に進んできました。今はまだ指を固定して弾ける曲ばかりですから、正しい位置に指をセットしていれば 鍵盤を見なくても弾ける曲ばかり。それと同時に音読み学習をしてもらっていますので、音読みもバッチリ。鍵盤を見なくても上手に弾くことができて います。ちゃんと顔が楽譜の音を追っています。この状態でピアノは弾いて欲しいのです。
ピアノ学習が進んで固定の指で弾けなくなった曲の 演奏でも、基本的には顔は楽譜を見ながら弾くようにします。音の跳躍など広がった鍵盤を使うときは、ミスタッチを防ぐために鍵盤を見て弾くことに なりますが、それ以外の時はやっぱり目は楽譜を追って弾きます。パソコンのキーボードで言う「ブラインドタッチ」でピアノも弾けるようにしていきましょう。 そのためには、小さな時から楽譜をだけを見て弾けるように癖をつけておく必要があります。もちろん楽譜を見た時に音がパッとわからなければ楽譜を見る 理由がありませんから、音読み学習も進めます。自分では気がつかないかもしれませんが、鍵盤ばかり(下ばかり)見てピアノを弾いている姿って、格好の 良いものではありません。はっきり言って格好は悪いです。堂々と弾いているようにも見えませんし・・・。ぜひ、楽譜だけを見て弾けるようにしていきましょう。
臨時記号はその音だけに適用されますが、臨時記号には臨時記号の決まりがあります。これを忘れてしまうと 変な曲・変な音になってしまいますから、必ず覚えておくようにしましょう。この写真の楽譜、1小節目のミの音にフラットが書いてあります。 1つ目のミの音にはフラットが書いてありますが、同じ小節のもう1つのミの音にはフラットの記号がありません。実はこれが臨時記号の 決まり事・約束事になります。臨時記号は同じ小節内であれば有効になります。ですから、最初に出てきたミの音のフラットは、同じ小節の中の他のミの音も フラットで弾くことになります。2つ目にはフラットの記号が書いていなくても勝手にフラットで弾く・・・これを忘れてしまわないようにしましょう。 時々生徒さんの中には「こっちには記号がついていなかったから」と、同じ小節の中にもかかわらず、白鍵で弾いてしまう生徒さんがおられますが、それは 間違い。臨時記号を学習する時には必ず、臨時記号の約束事のお話をしているはず。よ〜く覚えておいてくださいね。
この写真の楽譜、よく見ると 2小節目のミの音には新たにフラットがついています。これは小節が違うので、フラットの記号がついていなければ白鍵のミを弾くことになります。ですが、 この楽譜では臨時記号のフラットが書いてありますので、こちらのミの音も黒鍵になります。「臨時記号は、同じ小節内は有効」という臨時記号の約束事を 忘れないようにして、楽譜を読んでいくようにしていきましょう。
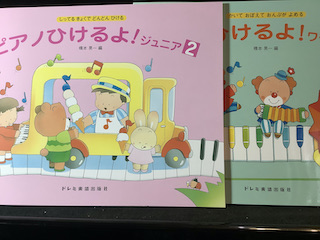 最近のピアノレッスンでの困ったこと、忘れ物をする生徒さんが多すぎる!今までにも、ちょこちょこと忘れてくる生徒さんはいらっしゃったのですが、ここ
最近は忘れ物をしてくる生徒さんの人数が増えています。毎週のように何らかを忘れてきてしまう生徒さんも。暑さのせい?そんなことはないと思いますが、
これって家を出る前に、ちょっとカバンの中を覗いたら気がつくのでは?レッスンに遅れないで来ることはもちろん大事ですが、早めにきて忘れ物をしてしまう
よりは、ちょっとくらい遅れても忘れ物をしない方がいいかなぁ。だって、いざ弾こうと思ったテキストが入っていなかったら、弾くものがありませんよ。
最近のピアノレッスンでの困ったこと、忘れ物をする生徒さんが多すぎる!今までにも、ちょこちょこと忘れてくる生徒さんはいらっしゃったのですが、ここ
最近は忘れ物をしてくる生徒さんの人数が増えています。毎週のように何らかを忘れてきてしまう生徒さんも。暑さのせい?そんなことはないと思いますが、
これって家を出る前に、ちょっとカバンの中を覗いたら気がつくのでは?レッスンに遅れないで来ることはもちろん大事ですが、早めにきて忘れ物をしてしまう
よりは、ちょっとくらい遅れても忘れ物をしない方がいいかなぁ。だって、いざ弾こうと思ったテキストが入っていなかったら、弾くものがありませんよ。
1番困る忘れ物は、弾くべきテキストを忘れていること。テキストはお一人お一人違いますし、注意されることも違っているので、自分のテキストが なければ書き込むことができません。せっかく練習をしてきた曲ですから、テキストの忘れ物だけは避けるようにしましょう。その他の例えば、ワークブックや 出席カード、レッスンノート、100曲マスターカードなどは、忘れてもいいものではありませんが、なければないで仕方がないなぁ・・・で終わらせることが できます。ただ100曲マスターカードについては、ご案内にも記してあるように忘れてしまったら合格曲のスタンプを持ち越せませんから、忘れないようにして おくのが良いかと思います。
特に注意をして欲しい生徒さんは、テキストを使用していなくてコピー楽譜を使用している生徒さんです。これって、 コピーしたままの楽譜ですと、はっきり言ってペラペラの紙。雑に扱っているとくしゃくしゃ状態になってしまい、楽譜なのかゴミ(失礼!)なのかわからなく なってしまいます。そのような状態になった楽譜を忘れている間に、最終的にはどっかにいっちゃった・・・なんてことになっている生徒さん。気をつけて 欲しいです。ファイルに入れるなり台紙に貼るなりして、大切に扱いましょう。そして、ファイルごと忘れてしまうことがないように注意をしてください。 忘れ物をすることのないよう、家を出る前にカバンの中の確認をお願いします。
こちらの生徒さん、曲が短くて簡単なことに加えて、練習量が すごいです。毎週のレッスンで、レッスン時間が足らなくて曲が進んでいかないほど(これは完全に私が悪いのですけど・・・)たくさんの曲を練習して くださいます。だって、レッスンを始めて5ヶ月での200曲の達成です。短い曲だから・・・・の理由だけではありません。とても頑張り屋さんです。
9月には 大泉学園でのピティナ・ステップにも参加をされます。小さな生徒さんだけあって、ピアノレッスンが予定通りに進まないこともあったり、ちょっとしたご機嫌 ナナメで弾けなかったりと大変なこともあるのですが、それらを全部ひっくるめて毎週のレッスンを頑張ってくれています。まぁ私も若くてキャピキャピ(?) した先生でもないので、生徒さんが泣こうが(泣かせているわけではありません。念のため)ご機嫌ナナメになろうが、動じませんけど・・・。ドンと構えて いますので、暴れてください(実際、暴れられるのは困りますけど?)そんなこんなで200曲を達成した生徒さん。マスターカードは12月までのカウントです から、ひょっとしたら300曲も達成してしまうかも?ですね。みんな、自分のペースで構いません。もちろん、たくさんの曲を練習された生徒さんは素晴らしい ことではありますが、無理をしてピアノが嫌いになりながらではなく、自分のペースで進められると良いと思います。1曲の曲が長くなってくると思うようように 進みませんからそれは仕方のないこと。楽しむ要素を取り入れながら、自分のペースで進めていきましょう。200曲達成、がんばったね!
 「来年は中学生だから、ピアノ無理になるかもしれません・・・」と、カミングアウトしたのは小学6年生ピアノ男子。ピアノが弾けるようになりたい・・・と
5年生の時に入会されました。習い初めてもう少しで1年。大人テキストでのレッスンを始めましたが、1年程度のピアノ歴だと、基礎の部分も終えていません。
「来年は中学生だから、ピアノ無理になるかもしれません・・・」と、カミングアウトしたのは小学6年生ピアノ男子。ピアノが弾けるようになりたい・・・と
5年生の時に入会されました。習い初めてもう少しで1年。大人テキストでのレッスンを始めましたが、1年程度のピアノ歴だと、基礎の部分も終えていません。
どの生徒さんにも共通して言えることは、自分で楽譜を読む力をつけたい・・・と思ってレッスンをしていること。いずれピアノ教室を卒業する ことになっても、自分で楽譜を読む力がついていればピアノを楽しむことができます。楽譜のイロハを知っていれば、弾きたい曲を弾くことができます。 その力をつけたいと思って、生徒さんたちへはレッスンをしています。だから、音読みにもこだわっています。小さい頃からピアノを学習している生徒さんは、 中学生になった段階では、自分で音楽やピアノを楽しめるところまでは到達している生徒さんがほとんど。そうなっていれば、あとは自分で楽しんでもらえたら よいのですが、大きな年齢でピアノ学習を始めた生徒さんであれば、やはり2〜3年の学習期間が欲しいでしょうか?
教室には11年目になる高校生の ピアノ男子、10年目のピアノ女子など、中学生・高校生の生徒さんが多数在籍されています。この生徒さんたちがピアノ教室に通い続けているのは、暇だから? そんなわけありません。生徒さんたちから話を聞いていても、皆さん忙しいです。中学受験・高校受験を終えられてもピアノを続けている生徒さんたち。 暇なはずがありません。忙しい合間を縫って時間を見つけて、それこそ隙間時間でピアノを練習をしている生徒さんもいらっしゃいます。朝の登校前にピアノを 弾いてから学校に向かう生徒さんも。習いたいピアノ・弾きたいピアノだから、上手に時間を見つけていらっしゃるのでしょう。
そもそも自分で 「無理、無理」と思うのなら、無理なのだと思います。だって自分自身が「できる」と信じていないもの、他の誰も信じられないです。「無理・できない」と 言ってしまうのは簡単なことですが、後ろ向きにばかり考えないで、前向きに自分のことを信じて取り組んでみることも大切です。何事も考え方や言葉かけ 1つで気持ちも変わっていきます。後ろ向きにマイナスのことばかり考えるのではなくて、前向きにプラス思考で考えてみませんか?お子様への言葉かけも、 前向きになれるような言葉かけが良いですね。「無理、できない」から始めるピアノではなく、「できる・やってみる」から始めるピアノにしませんか?
今までは「音読みやっておいてね」の声かけだけをしていました が、やってきていないのは明らかでした。これじゃ、いつまでたってもピアノは楽しくありません。だって思うように弾けないから。自宅でもいつも一人練習 で寂しい・・・と打ち明けてくれたことから、「レッスン中に一緒に音読みをしよう」と持ちかけて、音読みレッスンをすることにしました。音符カードを 生徒さんに読んでもらう、たったこれだけ。普通なら自宅で保護者の方や一人でやってもらうことを、私とやることにしました。「それ違うよ〜」「覚えて、 覚えて」など、和気藹々です。きっと、生徒さんにはこんな時間が必要だったのだと思います。レッスン中に私とカード読みをやっても、自宅では一人でやって もらわなければなりません。「教室でもやるけれど、自宅でも頑張ってみて」といった感じのレッスンが何ヶ月も続きました。写真では7月からの記録しか ありませんが、何ヶ月も頑張ってきました。そうして、ようやくレベル3の合格です。思うようにタイムが出ない中、生徒さんもよく続けてくれたと思います。 「やればできる!」を実感できたと思います。
少しづつですが毎週のピアノレッスンも好循環になってきていて、テキスト曲も前よりは弾けるように なってきました。1曲の仕上がりの時間が短くなってきています。16分音符の練習も時間はかかりましたが、伴奏と合わせて弾けるようになりました。1つが できるようになると、好循環に陥って全てがうまく回るようになります。反対に1つつまづいてしまうと、何もかもが嫌になる=悪循環・・・ってこと、子供 だけではなく大人でもあると思います。できれば好循環で物事を回したいですね。音符カード読みの第一弾はレベル4まで。少し読みづらいヘ音記号の低音部の音が 入ってきます。まだまだ私と一緒の音符カード読みは続きます。「やればできる!」を実践して、あとひと頑張りしていきましょう。
ピティナ・ステップに参加をされる生徒さんたちへは、1つ1つの動作をゆっくり・丁寧に行うように指導をしています。耳にタコができるくらいに何度も
何度も伝えていることは、膝の上に手を置くこと。演奏する前・演奏した後など、曲と曲の合間にも落ち着く時間を取るため、慌てないために、手を膝の
上に置くように指導しています。
前回のステップ参加者の行動で1つ気になったことがあります。それはお辞儀。演奏の前と後には舞台中央で 客席に向かってお辞儀をするのですが、その時に顔をあげたままお辞儀をしてしまった生徒さん。客席から見た時に、ずっと生徒さんの目が見えている 状態でした。ちょっと格好が悪いお辞儀になってしまいました。やはり顔は、あげたままではなく下げた方が良いです。あまりに下げすぎて転びそうになって しまうのはやり過ぎですが、ある程度は頭を下げないと見栄えがよくありません。生徒さんたちへ説明をする時の目安としては「自分のおへそをチラッと 見るように」とお話ししています。自分のおへそを見ることで、頭が下がる状態になります。やり過ぎているのかそうでないのかは、自宅練習でお辞儀の 練習をする時に、保護者の方が少し離れた位置から見てあげるようにすると良いと思います。注意をしながらお辞儀をしていると、頭の下げ方や角度などが 身についてきますから、これからは是非「本番練習」を取り入れていくようにしましょう。
9月のステップ本番まで1ヶ月を切ってきました。演奏に 不安のある生徒さんはいらっしゃらないので、1つ1つの動作確認や衣装の確認、靴の確認などもそろそろやっておくと良いと思います。お子様の場合は成長も 早いですから、衣装の腕周りや靴のサイズも確認が必要です。本番当日に腕が思うように動かなかった・靴が窮屈だった・・・と言うことがないようにしたい もの。特にお子様は、こんな些細なことでも日頃の力が十分に発揮されないこともあります。保護者としては、十分に力が発揮されるように環境を整えて あげたいですね。1つ1つの動作、お辞儀の仕方も含めて確認をお願いします。
前回のステップ参加者の行動で1つ気になったことがあります。それはお辞儀。演奏の前と後には舞台中央で 客席に向かってお辞儀をするのですが、その時に顔をあげたままお辞儀をしてしまった生徒さん。客席から見た時に、ずっと生徒さんの目が見えている 状態でした。ちょっと格好が悪いお辞儀になってしまいました。やはり顔は、あげたままではなく下げた方が良いです。あまりに下げすぎて転びそうになって しまうのはやり過ぎですが、ある程度は頭を下げないと見栄えがよくありません。生徒さんたちへ説明をする時の目安としては「自分のおへそをチラッと 見るように」とお話ししています。自分のおへそを見ることで、頭が下がる状態になります。やり過ぎているのかそうでないのかは、自宅練習でお辞儀の 練習をする時に、保護者の方が少し離れた位置から見てあげるようにすると良いと思います。注意をしながらお辞儀をしていると、頭の下げ方や角度などが 身についてきますから、これからは是非「本番練習」を取り入れていくようにしましょう。
9月のステップ本番まで1ヶ月を切ってきました。演奏に 不安のある生徒さんはいらっしゃらないので、1つ1つの動作確認や衣装の確認、靴の確認などもそろそろやっておくと良いと思います。お子様の場合は成長も 早いですから、衣装の腕周りや靴のサイズも確認が必要です。本番当日に腕が思うように動かなかった・靴が窮屈だった・・・と言うことがないようにしたい もの。特にお子様は、こんな些細なことでも日頃の力が十分に発揮されないこともあります。保護者としては、十分に力が発揮されるように環境を整えて あげたいですね。1つ1つの動作、お辞儀の仕方も含めて確認をお願いします。
高校2年生でレッスンを始められた生徒さんは、ほぼほぼ初心者状態でのレッスン開始でした。小さい時に2年ほどピアノを習った経験があったそうですが、 長い間、ピアノの鍵盤に触れていない状態。指がしっかり鍵盤を押せていないので、音はふにゃふにゃ。指強化や音符読みの学習をしてもらいました。 これまでの音楽の授業の下地があるので、音読みについてはすぐにできるようになり、大学生になる頃には両手で演奏できる状態になりました。まぁ、でも 本当に大変なのは大学生になってからで、弾き歌いやピアノ練習などの課題が山のように出てきます。その度に課題曲の練習をしてきました。
学校の試験曲は、弾き歌い2曲、ピアノソロ曲1曲。弾き歌いもピアノソロ曲も、強弱や曲の速さなどには気をつけなければなりません。特に弾き歌いは、声の 大きさや歌い方(楽しそうに歌っているかどうか)にも注意が必要で、ソロ曲を弾いている時よりも神経を使います。ただ歌っていれば良い・・・とは ならないところが難しいです。(笑)どちらの試験曲も、表現力についてうるさく指導をしています。旋律の動きやバスの音の動きに合わせての音の大きさ、 気持ちの込め方など、これ、私が1番うるさく言うこと。まぁ、生徒さんに言っているだけだから簡単だよね〜アハハ。でもでも、曲って本来そういうことに 気をつけて演奏するもの。ここは力を抜けないところです。細かな音の動きにも生徒さんは応えてくれて、素晴らしい演奏になりました。やったね!
生徒さんからの話を聞くと、実はA評価の上にS評価もあるとのこと。そう言えば大学の成績ってS,A,B,C・・・だったっけ?「じゃ、次はSを目指していき ましょう」と、生徒さんに提案をしたのですが「Sはなかなかもらえない」とのこと。ピティナ・ステップでの評価でもSってなかなかもらえないもんね。 A評価ならばかなり上出来ですから、それと一緒かな?ここから成績を落とさないように頑張っていきたいですね。細かな指導になりますが、どうぞ任せて くださいな。単位は落とさせませんよ〜。頑張っていきましょう。